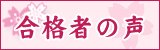第57回 税理士試験 試験解答財 法人税法
第57回 税理士試験 消費税法
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
消費税法
第1問
問1
1. 概要
国内において行った課税仕入れについて、返品をした場合又は値引きを受けた場合には、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用があり、保税地域から引き取った課税貨物について、違約品として再輸出した場合には、保税地域からの引取に係る課税貨物につき還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がある。なお、保税地域から引き取った課税貨物につき値引きを受けた場合には、還付を受けるべき消費税額がないので、上記特例の適用はない。
2. 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- [1] 取扱い
- 事業者(免税事業者を除く。)が国内において行った課税仕入れにつき、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、次の区分に応じ次に定める金額をその仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
- (1) 課税売上割合が95%以上である場合
- その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(その支払対価の額につき返還を受けた金額又はその減額を受けた債務の額に4/105を乗じて計算した金額。以下同じ。)の合計額を控除した残額
- (2) 個別対応方式により計算する場合
- ①に掲げる金額に②に掲げる金額を加算した金額
- ① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき、その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
- ② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合(課税売上割合に準ずる割合の適用がある場合にはその割合。以下(2)において同じ。)を乗じて計算した金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき、その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
- (3) 一括比例配分方式により計算する場合
- その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額からその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
- [2] 控除しきれない金額がある場合
- 上記[1]の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額をその仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして一定の金額をその課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
3. 保税地域からの引取りに係る課税貨物につき還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- [1] 取扱い
- 事業者(免税事業者を除く。)が保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の場合の区分に応じ、それぞれに定める金額をその還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
- (1) 課税売上割合が95%以上の場合
- その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額)から保税地域からの引取りに係る課税貨物につきその課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する金額を除く。以下同じ。)の合計額を控除した残額
- (2) 個別対応方式により計算する場合
-
- ①に掲げる金額に②に掲げる金額を加算した金額
- ① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額)から課税資産の譲渡等のみに要する課税貨物につき、その課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額
- ② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合(課税売上割合に準ずる割合の適用がある場合にはその割合。以下②において同じ。)を乗じて計算した金額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につきその課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
- (3) 一括比例配分方式により計算する場合
- その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額)から課税貨物につきその課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
- [2] 控除しきれない金額がある場合
- 上記[1]の規定により、還付を受ける消費税額の合計額をその還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、一定の金額をその課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
問2
1. 概要
- [1] 旧債権者
-
- (1) 金銭債権の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地により行う。事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、課税の対象となる。
- (2) 課税の対象となる場合には、金銭債権の譲渡は有価証券に類するものの譲渡に該当し、非課税となる。
- (3) 承継金額90万円の取扱いについては、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。ただし、当該金銭債権が資産の譲渡等の対価として取得したものである場合にはこの限りでない。
なお、新債権者が非居住者に該当する場合であっても、金銭債権の輸出は非課税資産の輸出取引等に含まれないことから、非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定の適用はない。
- [2] 新債権者
- (1) 金銭債権の譲受けが国内において行われたかどうかの判定は、その行為を行う者のその行為に係る事務所等の所在地により行う。事務所等の所在地が国内である場合には、国内取引に該当し、課税の対象となる。
- (2) 課税の対象となる場合には、利子を対価とする金銭の貸付け等に該当し、非課税となる。
- (3) 課税売上割合の計算上、債権金額と承継金額との差額10万円が資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
なお、当該金銭債権に係る債務者が非居住者である場合には、上記差額10万円は、非課税資産の輸出取引等に該当し、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ計上される。
2. 根拠法令
- [1] 課税の対象
-
- (1) 課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。 - (2) 資産の譲渡等
業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
① 資産の譲渡等に類する行為
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継 - (3) 国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
① 金銭債権の譲渡の場合
金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
② 金銭の貸付け等の場合
貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地
- (1) 課税の対象
- [2] 非課税取引
- 国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
- (1) 有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。)及び一定の支払手段(収集品及び販売用の支払手段を除く。)その他これらに類するものとして一定のものの譲渡
- (2) 利子を対価とする貸付金その他の金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託又は公社債投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
- [3] 課税売上割合の計算方法
-
- (1) 課税売上割合
次の①に掲げる金額のうちに②に掲げる金額の占める割合をいう。
① その事業者がその課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
② その事業者がその課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額 - (2) 資産の譲渡等に含まれないもの
上記(1)の資産の譲渡等には、金銭債権のうち資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡は含まないものとする。 - (2)金銭債権の譲受け
貸付金その他の金銭債権の譲受け等が行われた場合における対価は、利子等とする。
- (1) 課税売上割合
- [4] 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等を行った場合
-
- (1) 取扱い
- 事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき一定の証明がされたときは、その非課税資産の譲渡等のうちその証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
- (2) 課税売上割合の計算
- 課税売上割合の計算については、国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうちその輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
- (3) 適用除外
- 金銭債権の輸出は、上記(1)には含まれないものとする。
第二問
1 納税義務の有無の判定
計算過程
〔当課税期間前の納税義務の有無の判定〕
- 1、 前々課税期間
- (1)原則
基準期間なし
(2)特例
①
②
③ - 2、 前課税期間
- (1) 原則
基準期間なし
(2)特例
①
②
③
〔当課税期間の納税義務の有無の判定〕
- 1、 原則
- (1)
(2) - 2、 特例
- (1) (351,771,773円-5,249,100円)+(492,550,836円-428,900円)= 838,644,609円
(2)
(3) (1)-(2)=795,138,153円
(4)
(注) 特定要件の判定
2課税標準に対する消費税額の計算
| 区分 | 金額 | 計算過程 |
| 課税 標準額 |
180,278,000円 | 課税標準額の計算〕 77,432,835円+51,621,890円+31,242,636円+26,254,800円 +201,000円+160,500円+1,180,000円+(1,284,570円-284,570円) +(486,000円-287,500円)=189,292,161円 (千円未満切捨) |
| 課税標準に 対する 消費税額 |
7,211,120円 | 〔課税標準に対する消費税額の計算〕 180,278,000円×4%=7,211,120円 |
| 控除過大 調整税額 |
2,000円 | 〔貸倒回収に係る消費税額の計算〕 |
仕入れに係る消費税額の計算等
| 区分 | 金額 | 計算過程 |
| 課税売上 割合 |
〔課税売上割合の計算〕 ③ 輸出免税売上高 ∴仕入税額は按分計算が必要 |
|
| 控除対象 仕入税額 |
5,567,960円 |
〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 (ロ) 仕入に係る返還等 (ハ) 課税貨物に係る消費税額 ③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの (2) 個別対応方式 (3) 一括比例配分方式 (4)(2)>(3) ∴ 5,567,960円 |
|
〔調整対象固定資産に係る控除税額の調整の計算等〕 ② 乗用車 (2) 著しい変動 (3) 転用に係る調整税額 |
||
| 〔控除対象仕入税額の計算〕 | ||
| 売上げの 返還等対価 に係る税額 |
25,039円 | 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 |
| 貸倒れに 係る税額 |
5,041円 | 〔貸倒れに係る税額〕 |
| 控除税額 小計 |
5,598,040円 | 〔控除税額小計の計算〕 5,567,960円+25,039円+5,041円=5,598,040円 |
差引税額の計算
| 区分 | 金額 | 計算過程 |
| 差引税額 | 1,615,000円 | 〔差引税額の計算〕 7,211,120円+2,000円-5,598,040円=1,615,080円→1,615,000円 (百円未満切捨) |
中間納付税額の計算
| 区分 | 金額 | 計算過程 |
| 中間納付税額 | 484,800円 |
〔中間納付税額の計算〕 (2) 三月中間申告 (3) 六月中間申告 (4) (1)+(2)+(3)=484,800円 |
納付税額の計算
| 区分 | 金額 | 計算過程 |
| 納付税額 | 1,130,200円 | 〔納付税額の計算〕 1,615,000円-484,800円=1,130,200円 |
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。