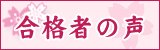平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 会計学(午前)
平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 会計学(午前)
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
会計学(午前)
第1問
問題1
問1
問2
問3
| 貢献利益率 |
70 % |
損益分岐点の売上高 |
69,940,000 円 |
| 安全余裕率 |
8.8 % |
|
問4
問5
| ①製品1個当たり変動費の引き下げ額 |
741 円 |
| ②年間固定費総額の引き下げ額 |
4,368,000 円 |
問6
- ①
- 変動費の引き下げ方策:仕入先の見直しや変更によって材料購入単価の削減を行い、また、製品設計自体を見直し、労働、作業能率を改善することによって、直接材料費、直接労務費、変動製造間接費の引き下げを行うことが考えられる。
- ②
- 固定費の引き下げ方策:短期的に削減可能な固定費である広告宣伝費、研究開発費等のマネジド・コストを削減することが考えられる。
問7
- ①
- 営業利益概念の違い:CVP分析による営業利益は、変動製造原価のみを製品原価とし、固定製造原価を期間原価とするため、販売量と比例した利益概念である。これに対し、全部標準原価計算による営業利益は固定製造原価も製品原価とするため、販売量のみならず生産量に影響される利益概念である。
- ②
- CVP分析が有効である理由:全部標準原価計算の営業利益は販売量のみならず、生産量にも影響される利益概念であることから利益計画策定には不向きであるが、CVP分析による営業利益は販売量に比例する利益概念であることから、利益計画策定には有効である。
ページTOPへ
問題2
問1
| ア |
10,878,819 円 |
イ |
40,259 円 |
問2
組別総合原価計算を行うにあたっての問題点:
現代は製品や製造工程の多様化に伴い、直接作業や機械稼働時間などには相関のない生産・販売支援活動費による間接費が増大してきている。にもかかわらず伝統的な組別総合原価計算では、間接費を直接作業時間などを用いて大雑把に配賦する結果、単純で大量に生産するものにより多くの組間接費が配賦され、設計が複雑だったり、頻繁に段取替えが必要な多品種少量生産品にあまり原価が配賦されない問題点が生じている。
問3
| ウ |
30,938,391 円 |
エ |
19,197,006 円 |
オ |
96,798 円 |
問4
活動をグループ別に分ける理由:
製品の生産に必要な諸活動には、その発生が工程の始めに集中するもの、全工程で平均的に発生するもの、終点に発生が集中するものなどがあり、工程のどの段階でどのように発生するかをグループ分けして、原価発生態様の似たものをまとめ、それぞれの原価態様にふさわしい方法で完成品と仕掛品に配分した方が、活動の実態をきめ細かに反映したより適切な原価計算を行うことができるから。
問5
相違をもたらした最大の要因:
伝統的な計算では、Pのように生産量が多く直接作業時間が多い製品に多くの間接費が配分される。しかしABCでは、設計や資材発注の比重が大きい製品Qにはそれらの間接費が多く配賦され、機械運転時間に関わる原価は製品Pに多く配賦される。しかも資源ドライバーを用いて活動費を計算した結果、グループⅠに関わる原価の比重が大きくなっ
ている。これがイよりもオの製品単価の方が倍以上大きくなる結果をもたらした要因である。
ページTOPへ
第2問
問題1
問1
問2
| ア |
3.017 |
イ |
2.317 |
ウ |
2.683 |
エ |
1.983 |
問3
| 構成部品 |
目標原価 |
最終見積原価 |
未達成額 |
| 金額(円) |
構成比率 |
金額(円) |
構成比率 |
金額(円) |
構成比率 |
| エンジン |
123,820 |
0.302 |
161,200 |
0.350 |
-37,380 |
-0.232 |
| ボディー |
95,120 |
0.232 |
115,800 |
0.252 |
-20,680 |
-0.179 |
| サスペンション |
109,880 |
0.268 |
103,000 |
0.224 |
6,880 |
0.067 |
| タイヤ |
81,180 |
0.198 |
80,000 |
0.174 |
1,180 |
0.015 |
| 計 |
410,000 |
1.000 |
460,000 |
1.000 |
-50,000 |
-0.109 |
問4
- 方策
- ①伝統的な原価計算システムに代えて、製造コストと環境負荷の削減の同時達成を意図するマテリアルフローコスト会計を導入する。
- ②商品企画の共用化・標準化による色使用、オプション部品、旧型サービス部品等で種類の削減やライフサイクルの見直し。
- ③物流システムに見直しによる、納入ロットや回数の適正化、共同配送化や荷姿の簡方策素化の実施。
①の方策が原価を低減できる理由:マテリアルフローコスト会計は、原料費や加工費の観点も考慮
し、歩留率や不良率を重視するため、その結果ロスコストを削減することによって原価の削減に役
立つ。
①の方策が環境負荷を低減できる理由:マテリアルフローコスト会計は廃棄処理、リサイクルに
投入された材料及び製造プロセスにおけるエネルギーロスも負のコストとして計数化し、分析、検
討されることで、省資源・省エネに役立つ。
ページTOPへ
問題2
問1
| ア |
貨幣の時間価値 |
イ |
金額 |
| ウ |
正味現在価値法 |
エ |
比率 |
| オ |
内部利益率法 |
|
問2
|
/
|
A案 |
B案 |
| 単純回収期間法 |
4.99 年 |
5.01 年 |
| ウの方法 |
1,048 千円 |
-15,665 千円 |
問3
問4
- 社長の主張:
- 当社の中期計画の数値目標の1つである3年後のCFROI30%に対して、A案は約28.9%である一方B案は約32.9%である。よって、B案を採用すべきである。
- 財務担当副社長の主張:
- B案はA案に比して回収期間も長く、正味現在価値もマイナスであるため採用すべきではなく、A案を採用すべきである。
問5
- メリット:
- 投資計画を時期的に分割することで、投資環境を見ながら続く投資の実行を判断できるメリットがある。つまり、投資環境が悪ければ投資をしなくて済むことになり、投資リスクを抑えることができる。
- 具体的な方法:
- これを評価する具体的な方法にはリアル・オプションという手法があり、本案はその中でも拡張オプションに対応した検討方法を採用することになる。
ページTOPへ
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。
お問い合わせはこちらからお願いします。
ページTOPへ