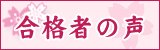平成19年 公認会計士試験 論文式試験解答 租税法
平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 租税法
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
租税法
第1問
問題1
問1
(番号)①
問2
Aに対し支出した祝金は寄附金に該当する。寄附金とは内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額等とされている(法法37⑦)が、広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものは除かれている。
Aは10年前にX社の一切の役職から退き、現在ではX社株式も所有していないため、金婚式の祝金はAがX社の経営に従事することの対価でもなく、またAは現在、X社の得意先、仕入先その他事業に関係のある者等にも該当しない。よって当該祝金は役員給与(法法34)、福利厚生費及び交際費等(措法61の4)のいずれにも該当しない。また広告宣伝費及び見本品費に該当しないことは支出の内容から明らかである。以上の事項すべてに該当しないことから寄附金であるといいうることができ、資本金等の額等を基準として算定した金額を超える部分が損金不算入となる(法法37①)。
問題2
問1
課税単位のあり方については、個人単位主義、夫婦単位主義、世帯単位主義の3つがあるが所得税は個人単位主義に基づく個人単位課税を採用している。この個人単位課税のもとでは所得を家族構成員の間で分散し、高い累進税率を排除して、租税の回避を図ろうとする傾向を招くことが想定される。そこで、これらを防止するために、同一生計の親族は事業に従事した者等に対する対価の支払いについては、所定の要件を満たす青色事業専従者給与の支給を除き、必要経費に算入しないこととしている。
問2
- ①
- AとBとは同一生計の親族である。このことから、所得税法第56条の適用により、AがBに対して支払った賃料は、Aの事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないこととなり、また、Bはその受取った賃料は、不動産所得の計算上ないものとされる。
- ②
- AとCとは別生計の親族である。このことから、所得税法第37条の適用により、AがCに対して支払った報酬は、Aの事業所得の計算上、必要経費に算入されることとなる。また、所得税法第27条及び第36条の適用により、Cが受取った報酬は、Cの事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。
- ③
- Aが事業の用に供している土地・建物は、Bの所有であり、Bがその固定資産税を支払っている。この場合には、所得税法第56条の適用により、当該固定資産税の金額は、Aの事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されることとなり、また、Bにおいては、その不動産所得の金額の計算上ないものとされる。
第2問
問題1
| 計算の明細 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 当期利益の額 | 1,668,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 加 算 | 減 算 | ||||||||||||||||||||||
| *解答にあたっての注事事項:加算すべき金額,減算すべき金額の合計額をそれぞれ右の加算,減算の欄に記入しなさい。なお,計算の明細の記載に当っては,加算すべき金額および減算すべき金額が共に生じない場合には,0(ゼロ)を明記しなさい。 (棚卸資産の評価について)
|
660,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
(減価償却資産の償却費について)
|
225,153 | 486,000 | |||||||||||||||||||||
(繰延資産等について)
|
9,700,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
(租税公課について)
|
1,208,345,000 | 183,700,000 | |||||||||||||||||||||
| (リース取引について) | 237,500 | 0 | |||||||||||||||||||||
(貸倒引当金及び貸倒損失について)
繰入限度額 18,566,100 |
20,933,900 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (交際費等について) | 4,352,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (外国税額控除について) | 49,500,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加算額・減算額の合計額 | 1,293,953,553 | 184,186,000 | |||||||||||||||||||||
| 法人税額の計算 | |||||||||||||||||||||||
| 課税所得金額 | 2,777,767,553 | ||||||||||||||||||||||
| 法人税額 | 833,330,100 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税額控除額 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
| 外国税額控除額 | 43,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 中間申告分の法人税額 | 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 納付すべき法人税額 | 390,300,100 | ||||||||||||||||||||||
問題2
| (1) 役員給与の損金不算入額 | 2,564,000 |
| (2) 給与所得の金額 | 16,540,000 |
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
- (1) 課税標準額
- 課税標準額(千円未満切捨)は, 641,985,000 円である。
- (2) 課税標準額に対する消費税額
- 課税標準額に対する消費税額は, 25,679,400 円である。
問2 仕入税額の按分計算の要否を判定する基礎となる課税売上高及び非課税売上高
- (1) 課税売上割合
- 課税売上高は, 670,033,600 円である。
- (2) 非課税売上高
- 非課税売上高は, 66,267,059 円である。
問3 個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額の計算
- (1) 課税売上げのみに要する課税仕入れ等の税額
- 課税売上げのみに要する課税仕入れ等の税額は, 20,069,520 円である。
- (2) 課税売上げと非課税売上げとに共通して要する課税仕入れ等の税額
- 課税売上げと非課税売上げとに共通して要する課税仕入れ等の税額(按分後税額)は, 3,236,018円である。
- (3) 個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
- 個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額は, 23,305,538 円である。
問4 一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額の計算
一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額は, 21,564,801 円である。
問5 納付すべき消費税額の計算
- (1) 控除対象仕入税額
- 控除対象仕入税額は, 23,305,538 円である。
- (2) 売上げに係る対価の返還等に係る消費税額
- 売上げに係る対価の返還等に係る消費税額は, 558,080 円である。
- (3) 差引税額(中間納付税額控除前の税額)
- 差引税額(百円未満切捨)は, 1,815,700
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。