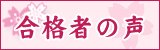平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 企業法
平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 企業法
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
企業法
第1問
問1
1
設問は、特定の株主との合意による自己株式の取得である。特に、自己株式の有償取得は、その対価いかんによっては、株主間に不公正が生じうる。そこで、その弊害に対処するために、手続規制が設けられている。すなわち、第1に、本来、株主との合意による自己株式の有償取得は株主総会の普通決議であるが、特定の株主との合意による自己株式の有償取得には、株主総会の特別決議が必要となる(160条1項・309条2項2号)。第2に、C以外の他の株主にも、自己を売主に追加するように請求する権利が与えられる(160条3項)。第3に、株主総会において売主となる株主(C及び追加請求をした他の株主)は、議決権を行使することができない(160条4項)。
2
また、株主との合意による自己株式の有償取得は、実質的に出資の払戻しで会社財産の減少となることから、規制がない場合には、会社債権者を害するおそれがある。そこで、その弊害に対処するために、財源規制が設けられている。すなわち、当該自己株式の取得によって株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該自己株式の取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(461条1項3号)。
問2
1 小問(1)について
株式併合とは、例えば、10株を1株として、より少数の株式数にすることをいう。この株式併合は、株主への影響が大きいことから、株主総会の特別決議が必要である(180条2項・309条2項4号)。そこで、Cを排除するというのは、Cを株主でなくするということであるから、その手続は、以下のようになる。第1に、株主総会の特別決議によって、例えば、1株を200株とする株式併合をする。この結果、Aは3.5株、Bは1株、Cは0.5株となって、Cは株主ではなくなる。第2に、端数の合計数に相当する数の株式を競売し、その代金を端数に応じて株主に交付する(235条)。以上、Cに金銭を交付し、甲会社から排除することになる。
2 小問(2)について
Cは、株式併合の行うための株主総会の決議の効力を否定することを通じて株式併合の効力を争うことが考えられる。この点、Cを排除することを目的とした株式併合のため株主総会の決議は、多数決の濫用として「著しく不当な決議」と考えられる。また、AとBは、取締役でもあるから、当該株主総会の決議について株主としての資格を離れた「特別の利害関係を有する者」に該当すると考えられる。とすると、当該株主総会の決議には、取消原因がある(831条1項3号)から、Cは、訴えをもって株主総会の決議を取り消し、株式併合の無効を主張することができると考える。
第2問
問1
1 手続について
甲会社と取締役Aとの取引は、いわゆる利益相反取引である。当該取引は、取締役がその地位を利用して会社に利益を犠牲にし、自己の利益を図る危険がある。そこで、Aは、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(356条1項2号)。この点、取締役会設置会社においては、取締役会の承認を受ければよい(365条1項)が、Aは、取引後、遅滞なく、重要な事実を取締役会に報告しなければならない(同2項)。取締役会による監督是正をしやすくするためである。
2 取引の効力について
(1) 株主総会(取締役会設置会社は、取締役会)の承認を受けないでなされた利益相反取引の効力については、明文の規定がない。しかし、原則として無効と考えるべきである。取引の相手方は取締役であるところ、手続を踏んでいない取締役を保護する必要はないからである。
(2) しかしながら、当該取引に関して第三者が登場した場合は、取引の安全を考慮する必要がある。したがって、この場合は、会社は、当該取引が無効であることを善意の第三者(甲会社とAとの取引が利益相反取引であって、会社の承認を受けていないことを知らない第三者)に主張することはできないと考えるべきである。
問2
甲会社は、監査役会設置会社であるから、取締役会設置会社でもある(327条1項2号)。しかし、取締役会の承認の有無にかかわらず、取締役が任務を怠ったことによって甲会社に損害が生じた場合、取締役は、甲会社に対し、損害賠償責任を負う(423条1項)。取締役会の承認に、取締役の会社に対する責任を免責する効力はないからである。そこで、取締役は、①任務懈怠と②過失があれば、会社に対し、損害賠償責任を負うが、利益相反取引は、会社に損害を与える危険性の大きい行為であるから、特則が定められている。
(1) まずAは、任務を怠ったものと推定され(428条3項1号)、自己のために利益相反取引をしているから、無過失責任である(428条1項)。また、責任を負う場合、株主総会や取締役会の決議による責任の一部免除(425条・426条)を受けることはできない(428条2項)から、総株主の同意がなければ、責任を免除することができない(424条)
(2) 一方、A以外の取締役のうち、甲会社がAと取引をすることを決定した取締役と、取締役会の承認決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定される(423条3項2号・3号)が、無過失責任ではない。また、責任を負う場合でも、株主総会又は取締役会の決議によって責任の一部免除(425条・426条)を受けることができる。
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。