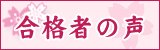平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 会計学(午後)
平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 会計学(午後)
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
会計学(午後)
第3問
問1
| ① | 1,600 百万円 | ② | 450 百万円 | ③ | -440 百万円 |
| ④ | 375 百万円 | ⑤ | -1,050 百万円 | ⑥ | 250 百万円 |
| ⑦ | 750 百万円 | ⑧ | -400 百万円 | ⑨ | -72 百万円 |
| ⑩ | 240 百万円 | ⑪ | -200 百万円 | ⑫ | 27,340 百万円 |
問2
(1)資産を過去の取引又は事象の結果として、財務諸表を報告する主体が支配している経済的資源、負債を過去の取引又は事象の結果として、報告主体の資産やサービス等の経済的資源を放棄したり引き渡したりする義務とすると、これらの差額がそのまま株主に帰属する資本となる保証はないため、資本とは必ずしも同じとはならない資産と負債との単なる差額を適切に示すように、「資本の部」という表記を「純資産の部」にかえた。
(2)財務報告における情報開示の中で、特に重要なのは、投資の成果を表す利益の情報であり、当該情報の主要な利用者であり受益者であるのは、報告主体の企業価値に関心を持つ当該報告主体の現在及び将来の株主であると考えられるため、当期純利益とこれを生み出す株主資本を重視し、株主に帰属するものであることを明確にする観点から、資産や負債に該当せず株主資本にも該当しないものも記載される純資産の部を株主資本とそれ以外の項目に区分することとした。
(3)連結貸借対照表上、株主資本以外の項目は、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分の3つに区分される。評価・換算差額等は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められてないことから株主資本とは区別されている。新株予約権は、株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によるものであり、また、少数株主持分は、子会社の資本のうち親会社に帰属してういない部分であり、いずれも親会社株主に帰属するものではないため、株主資本とは区別されている。
第4問
問1
(1)金券を交付する目的は、当期の商品売買を促進することである。そのため、金券交付取引の性格を、販売促進のための費用をもつ性格をもつ取引ととらえた上で、販売時の収益に対応する費用として商品の原価に相当する金額を費用計上する。
(2)①
| (借)現金 | 10,000 | (貸)売上 前受金 |
9,500 500 |
(2)②商品の販売と金券の交付を別々の取引と考え、金券の交付に相当する部分は、将来に使用が見込まれる部分であるから、最初から売上を控除するとともに、その部分については未だ商品を引き渡していないので、商品を引き渡す義務を負債として計上する。
問2
- (1)
- ①自己株式を取得したのみでは発行済株式総数が減少するわけではなく、取得後の処分もあり得る点に着目し、自己株式の保有は処分又は償却までの暫定的な状態であるとする考え方である。
- ②自己株式の取得を、自己株式の償却に類似する行為であるとする考え方である。
- (2)
- ①自己株式処分差損は、純資産の部の株主資本からの分配の性格を有し、その分配は、払込資本の払戻しと同様の性格を持つものであるとする考え方である。
- ②自己株式処分差損は、純資産の部の株主資本からの分配の性格を有し、その分配は、株主に対する会社財産の分配という点で利益配当と同様の性格であるとする考え方である。
問3
- (1)
- ①[負の現金同等物]とする取扱い。この取扱いは、当座借越が現金同等物と同様に利用され、資金管理活動の不可分な構成部分であるとする考え方を基礎にしている。
- ②[短期借入による収入]とする取扱い。この取扱いは、当座借越の状況が明らかに短期借入金と同様の資金管理活動と判断されるとする考え方を基礎にしている。
- (2)短期間に連続して借換えが行われる場合などにおいては、これらのキャッシュ・フローを総額表示すると、キャッシュ・フローの金額が大きくなり、かえってキャッシュ・フロー計算書の利用者の判断を誤らせるおそれがあるため、純額表示することが認められている。
- (3)
- ①検収から6ヶ月後の債務の支払については、有形固定資産の所得を原因とした債務に係る支出であるとする考え方を基礎にしている。
- ②検収から6ヶ月後の債務の支払については、資金の返済猶予を受けたものであるとする考え方を基礎にしている。
問4
(1)子会社株式を追加取得する事業分離について、事業に関する投資は継続しているとみなされ移転損益は認識されない。
(2)p2事業に対するP社の持分比率は100%から80%に減少する。P社の連結財務諸表において、P社の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係るP社の持分の減少額との間に生じる差額については、持分変動差額として取り扱う。
(3)s1事業に対するP社の持分比率は60%から80%に増加する。P社の連結財務諸表において、s1事業に対して追加投資したとみなされる額と、これに対するS社の事業分離直前の資本との間に生じる差額は、少数株主との取引に準じ、のれん(負ののれん)として処理する。
第5問
問1
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 200,080 千円 | 207,200 千円 | 265,450 千円 | 158,000 千円 | 24,000 千円 |
| ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 1,296,000 千円 | 38,000 千円 | 67,200 千円 | 90,000 千円 | 46,080 千円 |
問2
(1)「企業結合に係る特定勘定」の性格は、取得後短期間で発生することが予測される費用又は損失で、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合に認識した負債である。これは、認識の対象となった事象が発生した事業年度又は当該事象が発生しないことが明らかになった事業年度に取崩す。なお、企業結合日後5年以内に全額を取崩さなければならない。
(2)顧客リストは、法律上の権利ではないが、法律や契約により譲渡等が禁じられている場合を除き、分離して譲渡可能な無形資産に該当するため資産に計上することができ、また、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、当該金額を配分時に費用処理することとされているので、社長の支持する会計処理は認められる。
問3
(1)392,000 千円
(2)785,920 千円 ※or 800,000 千円
(3)減損処理は、投資期間全体を通じた投資額の回収可能性を評価し、投資額の回収が見込めなくなった時点で、将来に損失を繰り延べないために帳簿価額を減額する会計処理と考えると、減償却を修正して帳簿価額を回収可能な水準まで減額させる過年度修正について将来、遡及修正が行われるようになれば、減損損失の一部が減価償却の修正として処理されることになる。
問4
収益性の低下に基づき過大な帳簿価額を切り下げ、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理において、いったん費用処理した金額を正味売却価額が回復したからといって戻し入れることは、固定資産の減損処理と同様に適切ではなく、また、評価性引当金により間接的に費用処理を行うのではなく直接的に帳簿価額を切り下げるのであれば、切放し法が整合的といえるからである。
問5
いったん採用した数理計算上の差異の費用処理年数は、リストラによる大量退職等により平均残存勤務期間が延長又は短縮したことにより変更する場合を除き、継続して適用しなければならない。したがって、平均残存勤務期間にわたり費用処理している会社が、利益の多寡やビッグ・バス会計を理由に費用処理年数を変更することはできないため、社長が主張する会計処理は認められない。
問6
売却時に再購入する同時の契約を行い、決算日直後に売却価格と同一の価格で再購入した場合には、「譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」という金融資産の消滅の認識要件を満たさないため、売却処理は認められない。したがって、D社株式の売却に係る投資有価証券売却益を計上することは認められない。
問7
決算会議において修正の検討がなされた会計処理を行った場合、会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との間に差異が生じ、そのため一時差異の追加発生が予想される。
したがって、この一時差異(将来減算一時差異)に対する税効果会計の適用が必要となるが、その税効果会計の適用にあたっては、繰延税金資産の回収可能性について慎重に判断をする必要があることに留意しなければならない。
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。