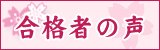平成19年 公認会計士試験 論文式試験解答 民法
平成20年 公認会計士試験 論文式試験解答 民法
※ご覧になりたい科目をクリックしてください
民 法
第5問
問1
- 1
- Cは、代理権の範囲内で甲土地の売買契約を締結しているから、その代理行為の効果はAに帰
属するのが原則である(99条1項)。しかし、Cには自己の利益を図る意図があるから、Aに代
理行為の無効を主張させて、その保護が図れないか。すなわち、客観的には代理権の範囲内にあ
るが、代理人に濫用意図がある場合、どのような理論構成で本人を保護するかが問題となる。 - 2
- 代理権を濫用している代理人には、自己の利益を図る意思と本人に法律効果を帰属させる表示
とに不一致があり、これは心理留保に類似する。そこで、相手方が濫用の意図につき悪意または
有過失の場合、本人は、代理行為の無効を主張できると考える(93条ただし書類推適用)。
- 3
- 本問では、Cの意図につきBが善意・無過失の場合、Aは、甲土地の所有権を主張できないから、所有権移転登記の抹消は請求できない。これに対して、Cの意図につきBが悪意または有過失の場合、Aは、甲土地の所有権を主張できるから、Bに所有権移転登記の抹消を請求できる。なお、この場合でも、代金を受け取っていないAには「利益」(703条)がないから、Bは、Aに代金の返還は請求できない。
問2
- 1 設問前段について
- AB間の売買契約は、Aの取消し(96条1項)により遡及的に無効となるため(121条本文)、B
は、甲土地につき無権利者となる。そして、登記には公信力が認められていない(192条反対解
釈)。したがって、Cは、B名義の登記を善意・無過失で信頼しても、甲土地の所有権を取得で
きないのが原則である。しかし、これでは一度取消しの意思表示をすれば登記を放置していても
第三者は保護されず、不動産取引の安全を害する。そこで、第三者の保護が問題となる。
取消しにより復帰的物権変動があったものと考え、取消権者と第三者間は対抗問題として177
条を適用すべきである。なぜなら、取消しの遡及効は一種の法的擬制にすぎず、物権変動があっ
たのは事実だし、被強迫者は取消後ならば登記を回復できるから不利益を課されても仕方ないか
らである。
本問では、甲土地の所有権は登記を回復したAに確定的に帰属する一方で、Dは無権利者に確
定するので、Aから甲土地を買い受けたEに所有権が帰属する。 - 2 設問後段について
- Fは平成16年に甲土地を時効取得(162条2項)しているが、平成18年に甲土地の所有権を回復
したAからEがそれを買い受けている。そこで、時効取得者と時効完成後の第三者の関係が問題
となる。
時効取得者は、177条により、時効完成後の第三者には登記なくして時効取得を対抗できないと
考える。なぜなら、時効完成により原所有者から時効取得者への実質的な所有権の移転があり、
その後の原所有者から第三者への譲渡に着目すれば二重譲渡に類似する状況にあるし、時効完成
後ならば登記は可能なので時効取得者が不利益を受けてもやむをえないからである。
本問では、F・Eともに登記を経由していないから、先に登記を経由した方に甲土地の所有権
が帰属する。
以上
第6問
問1
- 1 Cの賃料請求について
- Bが乙号室の引渡しを受けて賃借権の対抗力(借地借家法31条)を有しているので、Aの賃貸
人たる地位は、甲マンションの所有権とともにCに移転し、これにつきBの同意は不要と考える。
なぜなら、Cは居住できないのなら賃貸人としてBに賃料を請求したいと考えるのが通常だし、
Cの債務は所有者であれば誰でも履行できるので、Bに不利益はないからである。そして、Bの
賃料の二重払いを防止するため、Cが賃料を請求するには、登記という明確な基準が必要である
と考える。
よって、Cは、所有権登記を経由していれば、Bに賃料を請求できる。 - 2 Cの解除について
- 賃借人Bの債務不履行に対する解除についての特別規定はないが、解除の一般規定である541
条を適用すべきである。ただし、賃貸借契約は当事者の信頼関係を基礎とするし、軽微な義務違
反での解除を認めると賃借人に酷な場合もある。そこで、賃貸借当事者の信頼関係が破壊される
るに至っていない場合は、解除できないと考える。
Bは数ヶ月に渡って賃料を滞納しており、これによりB・C間の信頼関係が破壊されていると
いえる場合、Cは、所有権移転登記を経由していれば、賃貸借契約を解除できる。 - 3 Bの敷金に関する主張について
- 賃貸人たる地位の移転に伴って敷金返還債務もCに移転すると考える。なぜなら、敷金は、賃
貸人の債権を担保するものとして賃貸借契約に付随し、賃貸人の地位に随伴して移転するという
のが当事者の意思だからである。また、敷金は、賃借人が明渡しまでに負担する一切の債務を担
保するものであり、敷金返還請求権が発生するのは明渡しの時だから、敷金返還と明渡しは同時
履行(533条)の関係にはないと考える。
よって、Bは、未払賃料分を控除した敷金の返還をCに主張できるが、そのためには乙号室を
先に明け渡す必要がある。
問2
- 1 契約責任の追及について
- Dは、Bに賃貸人としての瑕疵担保責任(559条・570条)は追及できない。なぜなら、瑕疵担
保責任は有償契約の対価的均衡を維持する趣旨であり、瑕疵から拡大した怪我による損害の填補
までは予定していないからである。しかし、Bには、賃貸人として、Dの生命・身体の安全に配
慮し、危険のない居室を引き渡す信義則(1条2項)上の義務があるから、Bにその義務違反が
あれば、Dは、Bに債務不履行責任(415条)を追及できる。もっとも、Dは、A・F・Gには債
務不履行責任は追及できない。なぜなら、AはDに義務を負っていない(613条1項参照)し、D
とF・G間には契約関係がないためである。
Eは、誰にも債務不履行責任は追及できない。なぜなら、いずれの者との間にも契約関係がな
いためである。 - 2 不法行為責任の追及について
- D・Eは、天井の保存の瑕疵についてBに過失があれば、Bに工作物責任(717条1項本文)を
追及できる。なぜなら、間接占有者Bも「占有者」に他ならないからである。また、D・Eは、
Bが保存の瑕疵につき過失がなかったことを証明したときでも、Aに工作物責任(711条1項ただ
し書)を追及できる。なぜなら、Aは「所有者」として二次的に無過失責任を負っているからで
ある。
D・Eは、一般的不法行為責任(709条)をGに追及できるが、Fには追及できない。なぜなら、
Gには設計につき過失があるが、Fには施工につき過失はないからである。
以上
上記解答について
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。